こんにちは!こくうです。
今回は「教える側も教わる側も思いやりは大切」だと感じる場面について書いていきたいと思います。
仕事や学校などで「教える」「教わる」という経験は殆どの方が経験されていると思います。
今回は仕事での話になりますが、教える側も教わる側も思いやりは大切だと感じる場面が何度かありました。
会社で仕事をする上で、他の人との関わりは殆どの場合必要不可欠になってきます。
そんな中、引き継ぎなどで折角仕事を教えている・教わっているときに雰囲気が悪くなることは避けたいですよね?
そんな場面を避けるためにも、是非今回の記事でこんなこともあるんだと参考にしていただけたら幸いです。
「教える側も教わる側も思いやりは大切」だと感じる場面2つ
早速「教える側も教わる側も思いやりは大切」だと感じる場面を2つ書いていきたいと思います。
- 思っているよりも教えている側は反応を見ている
- 教わる側も聞いていいか迷っていることもある
詳しく書いていきます。
思っているよりも教えている側は反応を見ている
新入社員の方に仕事を教える側になったり、教育係をしている方の話を聞くと、
- 反応が薄くて理解したのかわからない
- 嫌そうにしているのが伝わってくる
ということがあります。
教えている側というのは、教わっている側が思っているよりも実はその人の反応を見ています。
分かったかな、難しかったかななど悩みながら教えているという事も少なくはありません。
そんなとき、上記のような反応だと「わかってはいそうだけど、大丈夫かな」「なんだかこの仕事やりたくなさそうな反応だな」と感じる場面も実は多々あります。
教えている側は自分の仕事の手を止めて教えていることも少なくありません。
教えるのも仕事とはわかっていても、恐らく気分のいいものではありませんよね?
自分が教える側の立場になった時に、同じような反応をされてしまったらと考えてみることも大切です。
もちろん、ずっとにこやかにしているべきということではなくて、
お互いに気持ちのいい受け答えになるよう心がけるということも、
他人と過ごす会社という場所では大切になってくるということを頭の隅に置いておくことも大切です。
教わる側も聞いていいか迷っていることもある
1つ目は主に教える側の立場の話ですが、こちらは教わる側立場になった際の話です。
教わる側になった際に感じたのは「先輩も忙しそうだし、聞き辛いな」「これ、こういう処理でよかったかな」と、
質問をしたいタイミングで思い悩むことも多いと思います。
特に、入社したての頃は「こんなこと聞いていいのかな」と、悩んでしまったことが私も経験があります。
そんなとき、定期的に「わからないことがあったら聞いてね」と、声を掛けてくださった先輩の存在が、今思えばとてもありがたかったなと感じる場面があります。
もちろん、慣れてきたのにいつまでも声を掛けてもらうのを待っているのは良くないと思いますが、
教える側の方は、自分が教わる側だったときはどうだったかなと振り返って、必要なら声を掛けることも大切だと思います。
質問しやすい雰囲気作りも教える側の気遣いひとつで変わってくると思うので、意識してみるのもいいのではないでしょうか。
まとめ
ここまで「教える側も教わる側も思いやりは大切」だと感じる場面を書いてきました。
そもそもなぜこの記事を書いているのかというと、
- どんなに頑張って教えようと思っていても、反応が悪くて教えたくないという気持ちになってしまった
- 聞きたいけど中々聞けなくて、さらにわからなくなって悩んでしまう
という場面を見たり、経験してきたので同じように悩んでいる方の参考になったらと思って書いてきました。
もちろん必要以上に気にかけすぎるのも、気を使い過ぎるのも仕事を進める上ではよくないこともありますが、
雰囲気よく仕事を教えたり教わったりする上では、適当な気遣い思いやりも大切ではないかということが感じていただけたら幸いです。
今回の記事が同じように悩んでいる方の参考になっていたら嬉しいです。
ここまで読んでくださってありがとうございました!ではまた!

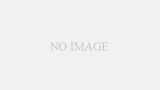
コメント